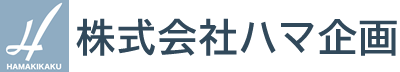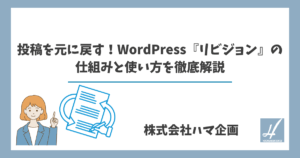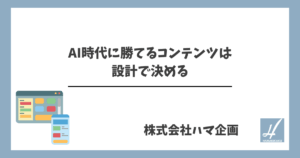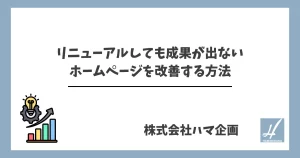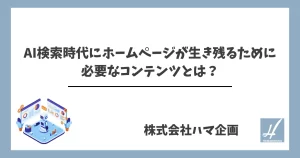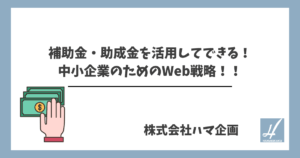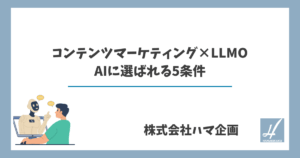ウェブアクセシビリティと聞いて皆さんはどのようなものなのかを想像することができますか?
私は聞いたことはあるけどどのようなことをするのかまではわかりませんでした。
私は以前、専門学校でウェブデザインを学んでいました。学校ではアクセシビリティについて知る機会はなく、学校を卒業してハマ企画に就職してから初めて知り、触れることになりました。
右も左もわからない中で始めたアクセシビリティチェックの作業は、想像以上に奥深く、多くの学びが詰まったものでした。
実際に作業を進める中で感じた苦労や達成感と重要性についてお伝えしたいと思います。
まずアクセシビリティとは

まずウェブアクセシビリティとは、すべての人が障害の有無にかかわらずウェブサイトを利用できるようにすることを意味します。例えば、視覚障害者の方でも音声読み上げソフトを使って内容を理解できたり、色覚に制限がある方でも正しく情報を得られるようにしたりといった工夫です。
アクセシビリティへの取り組みは、単に法律や規制を守るためだけではありません。
ウェブを利用する全ての人々に対して情報やサービスを公平に提供するための重要な手段であり、ウェブは私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。
そのため、すべての人が障害の有無に関係なく平等に情報やサービスを得ることができるようにするべきなのです。
ハマ企画の主な作業手順

自社で行っているウェブアクセシビリティチェックは、大まかに次のような手順で進めています。
- 対象ページの選定: チェック対象となるページを選び、全体の中から重点的に確認するページを決定します。
- 自動チェックツールを使用した検証: 自動化されたツール(エラーチェックツール、音声読み上げツール、コントラスト比チェックツール)を使って、ページの構造やエラーを機械的にチェックします。
- 手動による確認: キーボードのみで操作できるか、正しく読み上げられるかなど、実際に目で見たり耳で聞いたりしながら手動で検証を行います。
- エラーの整理と記録: 発見したエラーを一覧にまとめ、修正の優先度を決定します。
- クライアントへの報告と提案: エラーの内容をクライアントに報告し、修正方法について提案します。
- 再チェック: 修正後、再度アクセシビリティのチェックを行い、改善されたことを確認します。
アクセシビリティチェックで苦労した点

作業を開始して苦労した点が3点ありました。
内容が難しい
作業を開始して最初にぶつかったのは内容のむずかしさです。
アクセシビリティチェックの作業マニュアルを読んでも、内容が全く理解できませんでした。それは私自身に知識が一切なかったからです。そのため作業を始める前にまず知識を付けることからスタートしました。
チェックに必要なソフトが複雑
アクセシビリティチェックを行う際、サイトのエラーチェックツールや音声読み上げツール、コントラストチェックツールといった複数のツールを使用して自動的にチェックする作業が必要ですが、ツールによっては設定や使い方が複雑であり慣れるのに時間がかかりました。また徹底的に確認する必要があるためチェックをする箇所が多くかなり苦労しました。
手動での判断がある
エラーチェックツールだけでは対応できない問題、例えば「altテキストが適切かどうか」など、人の目で確認して判断する作業が多く残ります。これらの判断は、特に視覚に障害があるユーザーの立場に立って考える必要があり、経験のない私だけでは不安な部分が多々あるので簡単には結論を出せないことがありました。
このような苦労した経験と実際に手を動かして、アクセシビリティチェックの作業の大変さと重要性を身に染みて理解することができました。
アクセシビリティはビジネスにも影響がある
今回はアクセシビリティチェックの重要性とその難しさについてお伝えしました。
私はアクセシビリティに関して今まで触れたことがなかったのですが、触れてみて重要性と対応させることでのメリットを理解することができました。
アクセシビリティチェックを行うことでそのサービスを必要としているユーザーに対してより広範囲に情報をとどけることができます。そのためアクセシビリティ対応したサイトにすることで、自社で提供しているサービスを障害の有無に関わらずより広範囲に届けることができるため、ビジネスにも良い影響があります。
アクセシビリティに対応したサイトにすることで社会にとっても会社にとってもいい影響があるのです。