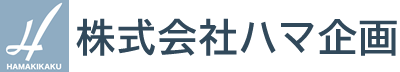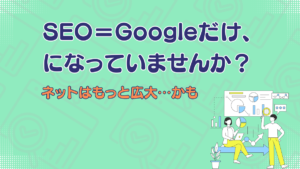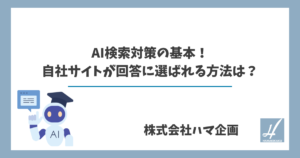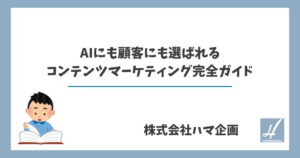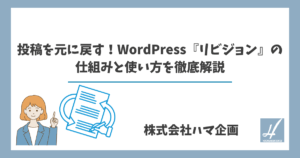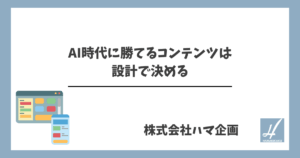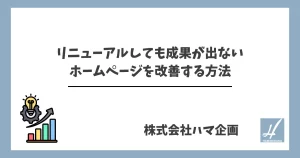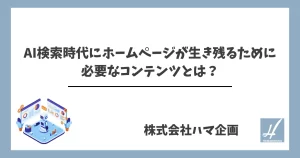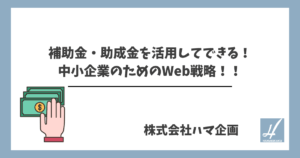仕事を効率よく、正確に進めるうえで欠かせないもの。それが「スケジュール」です。
どれだけ能力が高くても、スケジュールを立てずに仕事を始めてしまうと、思うように進まなかったり、他の人と連携が取れなかったりと、さまざまな問題が起きてしまいます。
スケジュールとは、単なる予定表ではありません。
自分の作業を「見える化」し、タスクを確実にこなすための「タスク表」でもあります。
それをもとに行動すれば、やるべきことが明確になり、仕事に対する不安も軽減されていきます。
ここでは、「スケジュールを立てないと、どうなるのか」や「スケジュールの立て方」についてお伝えします。
スケジュールを立てないと、どうなるのか?

スケジュールを立てずに進める仕事は、いわば地図なしで旅行をするようなものです。
行き当たりばったりで進めると、次のような問題が発生しがちです。
- タスクの漏れが発生する
目の前のことに集中しすぎて、他のやるべき作業を忘れてしまう。 - 納期に間に合わない
時間配分がうまくできず、最後になって焦ってしまい、クオリティも落ちる。 - 周囲に迷惑がかかる
自分の遅れが他の人の工程に影響してしまい、全体の進行が滞る。 - 優先順位がつけられない
重要なタスクを後回しにしてしまい、効率の悪い働き方になってしまう。 - 自分自身が疲弊する
「終わっていない仕事があるかも…」という不安に常に追われ、精神的にもしんどくなる。
実際私は案件を持ってすぐ、かなり納期が短かったので「スケジュールなんて立てる余裕ないからどんどん作業を進めないと」と考えていました。
ですが実際作業を進めようと思っても何をしたらいいかわからなくなり結果的に作業が遅れてしまい、タスクも漏れてしまう、漏れたタスクがかなり重要なタスクだったりかなり周りに迷惑をかけてしまいました。
新卒がやるべきスケジュールの立て方とは?

特に経験が浅い新卒の方がどのようにスケジュールを立てるべきかわからないという方も多いと思います。
ですがこれから紹介する4つの方法を意識するだけで完璧とまではいかないもののタスク漏れなどうっかりミスは確実に減ると思うので参考にしてみてください。
1. まずは上司に確認を取る
案件を受けたら、いきなり動き出すのではなく、上司と一緒にスケジュールを組むことが第一歩です。
初めて案件を持ち、何をしたらいいかわからないのは当たり前です。
まずは上司に何をしたらいいのか聞きながらスケジュールを立てましょう。
全体の流れや納期、優先順位など、わからない部分を埋めながら、完成イメージを共有しましょう。
2. 作業時間の“見積もり”をする
各作業にかかる時間をざっくりでいいので見積もっておくことで、無理のないスケジュールが作れます。
またスケジュール通りにいかないことがほとんどです。
予期せぬトラブルは確実に起こるものです。なので余裕を持った無理のないスケジュールを作る必要があります。
3. スケジュールは“細かく”立てる
「〇月〇日までに資料を作る」だけでは不十分です。
「調査(〇時間)→構成作成(〇時間)→初稿作成(〇時間)→上司に確認(〇時間)」のように、タスクを細分化しましょう。
細分化することで作業一つ一つにどのくらい時間がかかるのかがわかるためスケジュールを
4. 途中で確認ポイントを設ける
進めながら「このタイミングで上司に確認する」など、中間チェックのタイミングを設けることはとても大切です。
自分の考えだけで作業を進めてしまうと、上司やお客さんが望んでいるものとは違うものになってしまうことがあります。作業の途中でチェックを設けることで、方向性のズレを早めに修正できます。
細かいスケジュールが仕事を助ける
スケジュールを立てることで、仕事の全体像が見え、やるべきことがクリアになります。
タスクを忘れることもなくなり、納期に対する不安も減り、チームとの連携もスムーズに。
結果として、自信をもって仕事を進めることができるようになります。
新卒のうちは、わからないことが多くて当たり前です。
だからこそ、細かくスケジュールを立てることが、自分を守る最大の武器になります。
皆さんも、案件を受けたらまずスケジュールから。
しっかりとした設計図を描いて、着実にステップを踏んでいきましょう!