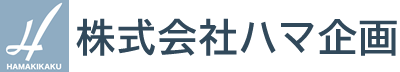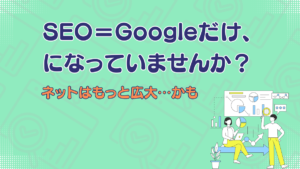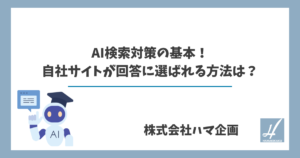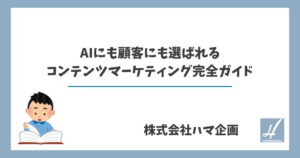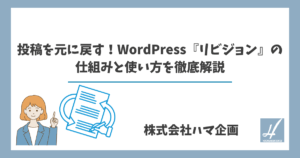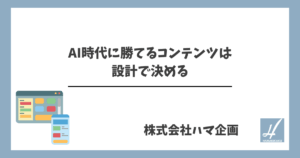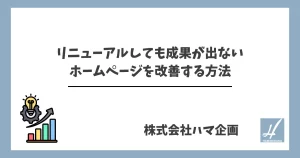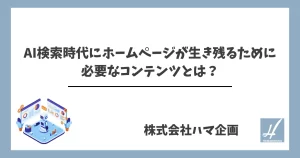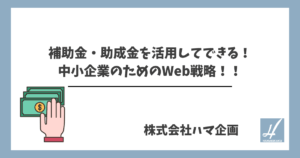「初めて学ぶウェブ解析」第11回です。
第8~10回では、事業計画立案についてわかりやすく解説しました。
今回は、実際にウェブ解析をするにあたって行う「設計」をまとめます!
マーケティング戦略でKGI・KSF・KPIが定まり、事業計画に基づいたウェブ解析を行います。
しかしいざ実際に行うとなると、何から始めればよいのか分からないはずです。
そこで行うのが、解析環境の設計における「ウェブ解析計画の立案」。
解析では多くの関係者が携わるため、たくさんのデータを取りまとめる「プロジェクトマネジメント力」が必要になります。
プロジェクトマネジメント力とは、計画の成功を目指して活動するための力。プロジェクトマネジメント力で「目的(何のために解析をするのか)」や「ゴール(何をいつまでに解析すればいいのか)」が明確になり、コミュニケーションや進行管理が同じ方向性で計画的にを進められるようになります。
ウェブ解析の前に決めること
解析計画を決める前に行うことが3つあります。
- ゴール
ゴールとは、目的の本質である「何のために/何を測定するのか」を検討すること。
まず、解析の目的で実装の「ゴール」を設定します。
ここで気をつける重要なことは、次の3つです。
・期日前にバッファ(余裕)を持っておく
・関係者に意見を求める
・内容に漏れや抜けがないか見直し、確認する - スコープ
スコープとは、計画内容における対象範囲のこと。
ゴールが決定すると、スコープが見えてくるのです。
ウェブ上では、容易に大量のデータが収集できるため、混乱の生じる可能性があります。
どの範囲のデータを対象にするかというスコープを定めると、欲しいデータが得られるようになります。 - 関係者
スコープに必要なデータに関わる関係者のこと。
スコープが決定すると、それぞれのデータを取得するのに関係者の協力が必要になります。協力者は必ずしも社内にいるとは限らないため、外部からの協力を仰ぐことは珍しくありません。
関係者を集めてウェブ解析をスムーズに開始できるよう、キックオフミーティングを実施します。
キックオフミーティングとは、目的に向かって行っていることを確認するための開始前の初回ミーティングのことです。
ウェブ解析を実行に移す計画
では実際に、ウェブ解析計画を実行に移す前に行うことがあります。
それは、計画立てる前に必要な情報と概要を決定させておくことです。
次の手順で5つです。
- 技術情報整理
サーバーやウェブサイト、自社内で利用しているサービスが「どこに/どのような情報が/どのような形で」存在するのかといったことを把握。技術情報整理を確認する場合は、オウンドメディアやアーンドメディア、ペイドメディアなどをチェックします。
オウンドメディアとは、ホームページやブログなどの自社で所有しているメディアのこと。アーンドメディアとは、SNSを利用してインフルエンサーなどの消費者から信頼や相互理解を獲得する必要があるメディアのこと。
ペイドメディアとは、ウェブ広告やCMなどの費用を払って広告を掲載する従来メディアのこと。 - 人員確保・教育
ウェブ解析を行うための関係者を集めます。
今後の導入と運用に関わる人員を確保し、解析の目的や技術的な説明などを行います。そうすることで、実装が円滑に進むようになるのです。 - 技術選定・導入
実際に導入する解析技術の選定を下の項目で行います。
・アクセス解析ツール
・アクセス解析補助ツール
・広告効果測定ツール
・ソーシャルメディア解析ツール - ウェブ解析のフェーズ決定
ここまで進めたら、下の表で「誰が/何を」するのか課題を具体的にします。項目
概要 実装
ウェブをカテゴリー別に分類し、実装を行うフェーズを検討する
試験運用
本運用前に各ツールの動作試験を行い、本運用で使用する データを確定させ、そのデータが予定通りに取得できているかを確認する
本運用 試験運用でデータ取得が安定すれば本運用を始め、
同時に関連部署への報告も行う - ウェブ解析計画の作成
ウェブ解析のフェーズ決定までの工程で計画に必要となる情報がすべて揃います。そしてこれを「ウェブ解析計画」という形で資料にまとめます。
ウェブ解析で利用する技術文書
ウェブ解析でサイトやシステムの状況をスムーズに把握するため、あらかじめ技術的環境の文書を用意しておきます。
そうすることで、担当者が変わっても混乱することはなくなります。
下の文書が実装前にあるか確認し、実装後にはアップデートして最新の状況に変更します。
- RFP(Request For Proposal)=提案依頼書
- SDR(Solution Design Reference)=分析実装の設計図
- タスクマネジメントツール実装指示書
- サイト/システム設計書
- UX/UI指示書
- SEO運用レポート/指示書
- ソーシャルメディア運用レポート/指示書
- 広告効果測定レポート
- 体制図・組織図
- セキュリティーポリシー・プライバシーポリシー・ガイドライン
- 事業計画・方針
- アジェンダ(議題)・議事録
RFPは、もっとも大切技術文書です。
RFPとは、新しいシステムや業務委託を希望するクライアントが依頼先に求める具体的な要件を記載し、作成する文書のことです。
内容を一括管理するために、ミーティング毎のアジェンダ(議題)と議事録は必須です。
いよいよウェブ解析の実装へ
実装段階では、下の4つに注意しながら進めていきます。
- システム環境の調整
- 検証環境への実装
- 本番環境への実装とタグマネジメントツールでのテスト
- 本番環境での実装
「3.本番環境への実装とタグマネジメントツールでのテスト」にある「タグ」とは、さまざまな機能をサイトに組み込むためのトラッキングコードのこと。
ウェブ解析の実装後はほとんどの場合、そのまま運用することはありません。
トラッキングコードなどに配慮しつつ、ウェブサイトなどにおけるシステム環境維持のため、チェックを行います。
そして解析ツールを利用し、テスト環境になっている状態でテストをします。
その後、本番環境へ移行させるのです。
さまざまな内的環境と外的環境の変化に伴って設定の変更が必要になってくるため、ウェブ解析の維持と改善のために行う内部要因と外部要因を挙げていきます。
〈内部要因〉
社内方針、システムやサイトにおける構造の変更によってメンテナンスが必要となるケース
- サイトフロー・ウェブシステム変更
- サーバー環境変更
- 関連システムや解析ツールの見通し
- マーケティング戦略変更
〈外部要因〉
インターネット環境や社会状況の変更によってメンテナンスが必要となるケース
- ウェブの環境の変化
- 法律や規制の変化
ウェブ解析は設計が大切
ウェブ解析では、多くの関係者が携わってたくさんのデータを取りまとめます。そのため、方向性の相違で事業計画がすべて失敗することもあるのです。
解析環境の設計で大切なことは、ゴールを決定させ、関係者1人1人がプロジェクトマネジメント力を意識し、同じ意志を持つことです。
それによって、解析環境の設計は上手くいくでしょう。