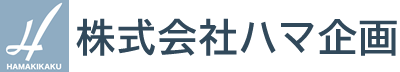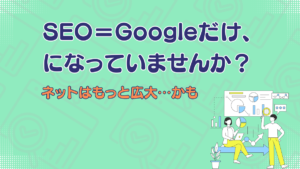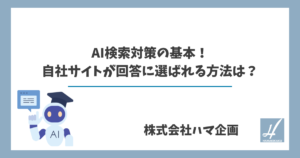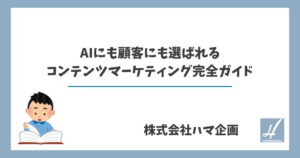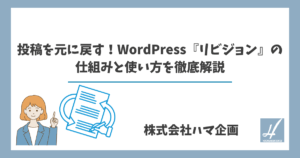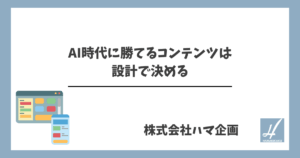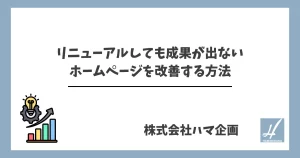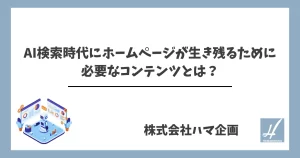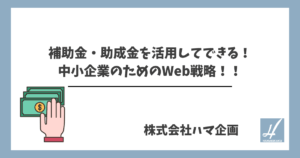ホームページは「作った後」がスタート
なぜ運用が必要なのか?
多くの中小企業や個人事業主が、ホームページを作る目的として「集客したい」「信用を得たい」「問い合わせを増やしたい」と考えています。しかし、ホームページは“完成した瞬間”にはまだ成果を生まないという現実があります。
なぜなら、検索エンジンに認識されるには一定の時間がかかり、訪問者が情報に触れるにはコンテンツの蓄積や導線設計が必要だからです。
制作直後のホームページは、いわば「看板を立てたばかりの無人店舗」のような状態。まずは道順を整え(SEO)、通行人に声をかけ(SNSや名刺掲載)、中の様子をわかりやすく伝える(コンテンツ)ことが重要です。
よくある“公開後に放置”の失敗例
ホームページ公開後にありがちな失敗パターンがこちらです。
- Googleにインデックスされておらず、検索しても出てこない
- お問い合わせフォームが壊れたまま気づかない
- ブログやお知らせが「〇年〇月で止まった」まま
- 制作会社に丸投げし続け、社内で活用されていない
これらはすべて「作って満足して終わってしまった」例。こうならないために、公開直後にチェックすべきことをリスト化してみましょう。
ホームページ制作後にやるべきことチェックリスト【10項目】
1.サーチコンソールとGA4の導入
Google Search Console(サーチコンソール)とGoogle Analytics 4(GA4)は、アクセス状況や検索パフォーマンスを測定するための必須ツールです。
Google Search Console(サーチコンソール)を導入すると「検索キーワード」「表示回数」「クリック数」が分かるようになります。
さらに、Google Analytics 4(GA4)を導入する事で、「訪問者数」「閲覧ページ」「時間帯」「流入元」などが分かるようになります。
導入後は最低でも月に一度、レポートを確認する習慣を作るとよいでしょう。
2. スマホ・各ブラウザでの表示チェック
パソコンでは綺麗に見えていても、スマートフォンやタブレットではレイアウトが崩れていることがあります。次の内容を手動で確認しましょう。
iPhone / Android 両方で、実際にサイトにアクセスをして表示確認をしてみましょう。
Chrome / Safari / Edge など異なるブラウザでも画面をクリックしたり、ぺージ移動してみたりと動作確認をしてみましょう。
スマートフォンやPCでも共通ですが、リンクやボタンが押しやすいか、文字が小さすぎないか、文章や見出しとのスペースは窮屈すぎないか等確認してみましょう。
見づらさは、直帰率(=すぐにページを閉じる割合)を上げる大きな要因です。
3.お問い合わせ・電話・フォームの動作確認
意外と多いのが、「お問い合わせフォームが動いていなかった」「メールが届いていなかった」というトラブルです。
実際にお問い合わせフォームからご自身でテスト送信して見ましょう、通知メールが正しく届いていますか?
電話リンク(スマホでタップできるか)もご自身でタップしてかかるかどうか試してみましょう。
また、ご自身で送信テストしたメールが迷惑メールフィルターに引っかかっていないかも要チェックです。
4. 各種SNSプロフィールのリンク更新
ホームページURLを変更・リニューアルした場合、Instagram・X(旧Twitter)・Facebook・YouTubeなどのSNSプロフィール欄のリンクも更新しましょう。
また、投稿や固定ツイートに「ホームページをリニューアルしました」などの情報を載せて、新サイトの存在を告知することも大切です。
5. メタ情報(タイトル・ディスクリプション)の最適化
検索結果に表示される「タイトル」と「説明文(ディスクリプション)」は、クリック率に直結する重要項目です。
実際の各ページのタイトルにキーワードが入っているかを確認してみましょう。
さらに説明文(ディスクリプション)が魅力的で内容がわかるか、ページの内容が要約されているか?も確認してみましょう。
合わせて、重複しているページがないかどうかも確認が必要です。
WordPressやCMSを使っていれば、SEOプラグイン(例:All in One SEO、Yoast SEO)で設定できます。
6.自社名・店舗名の検索順位チェック
「自社名(または店名)で検索して出てくるか?」は最初の確認ポイントです。
出てこない場合には、サイトにしっかり会社名・所在地・連絡先が入っているか、
サーチコンソールでURL登録sitemap.xmlの送信)リクエストを送ったか、
Googleビジネスプロフィールの登録は済んでいるかを必ず確認してみましょう。
まずは“指名検索”で表示されるようになることが第一歩です。
7.初期コンテンツの充実(ブログ・事例・お客様の声)
最低限以下のようなページ・コンテンツを用意しておくと安心です:
よくある質問(FAQ):これは実際にお客様からお問い合わせいただいた内容でも、
事前に説明しておきたいことでもかまいません。
施工事例/導入事例:新規のお客様が見たときに参考にしてもらえます。
可能であれば、お客様の声(レビュー)を掲載しておくと、こちらも新規のお客様の参考になります。
こちらも可能であれば、ブログやコラム(1〜3本)業務に関する内容を掲載しておくとよいでしょう。
「コンテンツが何もない」サイトは、Googleにもユーザーにも信頼されにくい傾向があります。
8.名刺や紙媒体へのURL記載
せっかくホームページを作ったのに、URLを印刷物に載せていないという事例も散見されます。
名刺、パンフレット、会社案内、チラシやDMには必ずURLやQRコードを掲載しましょう。新たに印刷するタイミングでなくても、シールなどで追加対応できることもありますので、必ず記載しましょう。
9. 社内での活用(営業・採用にどう使うか共有)
ホームページは「営業資料」としても「採用案内」としても使えるツールです。
例えば、営業担当に「このページを見せると説明が楽になる」ようなページを作成して、共有、実際にページを使ってもらいましょう。
採用希望者には「このページを事前に見ておいてください」と送ることで、その後の話がスムーズに進められます。
社内の全スタッフに「サイトにアクセスしてもらう」ことで、改善点が見つかる可能性も。
社内で共有されていないと、せっかくの制作が無駄になってしまいます。
10. 今後の更新・運用計画の立案
公開後の更新が止まってしまうと、検索順位にも悪影響があります。最低限以下を決めておき、常にサイトが更新されている状態を保つことが大切です。
最低でも月1回のブログ更新を目指し、運用しましょう。
ですが、業務に無関係な更新は避けた方がベターです。
新着情報はイベント・実績報告に使うことにより、再訪問されやすくなる可能性があります。
SNSと連動させて発信タイミングを統一すると尚よいでしょう。
半年〜1年に一度、トップページや導線の見直しを行い、改善点が見つかれば改善を行いましょう。
※可能であれば「運用担当者」を社内で決めるとスムーズです。
SEOや集客のためにすぐ始めたい3つのこと
ブログや事例ページの更新習慣を作る
「今すぐ始められてSEOにも効果的」なのが、ブログや事例紹介ページの更新です。更新を続けるのは大変ですが、以下のようなテーマが書きやすいかもしれません。
たとえば・・・
最近あったお客様とのやり取りやよくある質問への回答、スタッフの日常や現場風景などです。
月に1本でも継続できれば、サイトの“鮮度”と“信頼性”が保たれます。
SNS連携と発信タイミングの整備
ホームページを更新したら、SNSにも投稿しましょう。それにより新たなお客様がみつかることも・・・
ブログを更新したら SNSで告知(例:ブログ更新しました📢)をしましょう。
イベントがあるようなら、イベント告知を行い出来るならランディングページ( LP)を作成してとSNSを連携しましょう。
採用情報についても、 SNS経由での応募導線を持たせることで接触の可能性が増えます。
SNSを活用することで「フォロワー → サイト訪問者 → 問い合わせ」という導線が作れます。
Googleビジネスプロフィールの強化
飲食・小売・サービス業の場合、**Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)**の活用も必須です。
※社名標記は必ず統一!
最新情報や投稿機能を使って発信し、さらに口コミへの返信で信頼性アップします。
忘れてはいけないのは、ホームページへの誘導です!
SEOとMEO(マップ検索最適化)を両立するためにも、サイトと連携した運用が効果的です。
よくある質問(Q&A)と外注の判断基準
Q. 社内に更新できる人がいません…
→社内にIT担当がいない場合は、是非ハマ企画にご相談ください!
Q. SEOって何から始めればいいですか?
→まずは「検索されるキーワード」を意識したブログやコンテンツの更新を始めること。
Q. 制作会社とどう連携すればいい?
→「制作が終わったら終わり」ではなく、“パートナー”として定期的に相談できる制作会社が理想です。運用フェーズでのアドバイスや改善提案が受けられる体制があると安心です。
まとめ|ホームページを“活かす”第一歩を踏み出そう
ホームページは、作っただけでは意味がありません。
「公開後にどう動くか」で成果が決まります。
まずは今回ご紹介したチェックリストを参考に、
✔ 初期設定ができているか?
✔ 情報発信の仕組みができているか?
✔ 社内外で活用されているか?
を順に確認してみてください。
そして、無理のない範囲で運用の習慣を作り、育てていきましょう。
それが、“問い合わせが来るホームページ”への第一歩です。
ご不明点、ご相談などいつでもお問い合わせください!