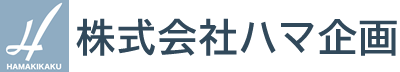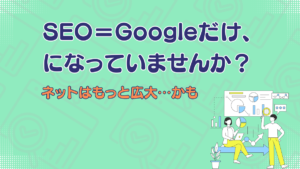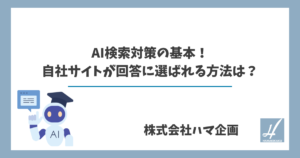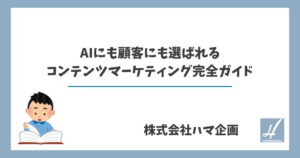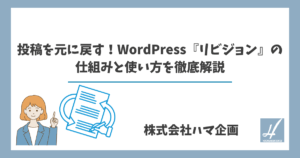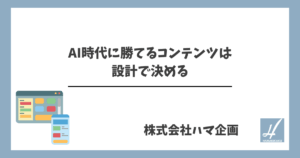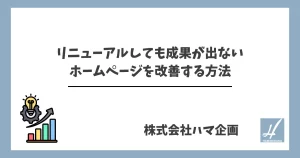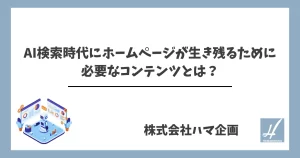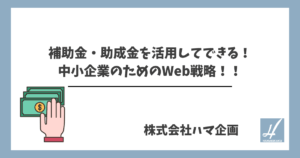仕事において、「準備8割」という言葉をよく耳にしますが、むしろ10割というくらい、準備が大切だと感じています。仕事は準備だけなんじゃないか、と思う事もあります。
最近しっかり準備したな、と思うのはお客様との打合せです。
打合せの「本番」は打合せそのものですが、「準備」は打合せの目的を再確認し、内容を言語化し(何を話すか、何を決めるか)、確実に伝えるためにどうするか(新しく資料を作るのか、既存の資料をどう見せるか)…などを考えて確認することでしょうか。
ところで、前職で私は店舗出店の現場監督などをしており、準備といえば結構本気でした。
例えば、出店準備期間で商品搬入をしている、とある1日だけを切り取ると、「準備」と「本番」の内容は簡単に、こんな感じです。
- 本番:「トラックから陳列棚や商品をおろして、皆で店舗に運び入庫作業をする」この一連の流れを指示して時間通りに終わらせる
- 準備:ロケーション確認、当日運ぶもの手配、スケジュール、メンバーへの指示内容を作成して確認
事前に商品の搬入経路の確認などをしておき、当日はトラックから陳列棚や商品をおろして皆で店舗に運び…という一連の流れの指示出しというメイン業務があるため、事前にスケジュール確認やメンバーへの指示内容を準備していました。
細かく上げればたくさんの準備をしましたが、やっていたことは、いかに当日(本番)をスムーズにマックスの出力でできるか、をひたすら考えて実行する事だと思います。回を重ねるごとに「もっとあれやっておけば…」が出てくるため、どんどんやることが増えましたが、当日はどんどんスムーズになりました。
何店舗か経験すると、当日現場で指示するポイントは変わらないので、自動運転モードでできてきます。
ただ、突発的で外部要因の「想定外の出来事」は起こるものなので、起こったときにきちんと対処できるよう、事前にやるべきことはやっておくことは非常に重大なことだと思うのです。
(例えば、「自分たちの台車のサイズが通路幅より大きくて台車が通らない」とかで騒いでいたら、その他の事が起こったときに対応できなくなりますよね。本来搬入経路と自社の台車のサイズの確認は事前に行う事であり、少なくとも、サイズの合わない台車を持参するという大惨事は起こさずに済みます)
さらに何度かやっていると、起こりそうな事故を経験から想定できるので、それにどう対応するか先に上司に確認しておき、さらに当日余裕を持っていられるようになります。
それらの準備をすることで、本来の目的である最低限のことはスムーズに、余計なことを考えずにできますし、想定外の事が起こっても、比較的落ち着ていて対応できます。
前置きが長くなりましたが、最近しっかり準備したのは「お客様との打ち合わせ」ですので、「打合せ」をテーマに準備について整理してみたいと思います。
打合せといっても色々あります。
- 新規のお客さんとの初回打合せの時
- 現在進行中のプロジェクトで、お客さんとの打合せの時
- 現在進行中のプロジェクトで、社内打ち合わせの時
など考えられますが、一旦「現在進行中のプロジェクトで、お客さんとの打合せの時」という場合を考えます。
なんで準備8割?
準備8割(以上)にこだわるのは、本番を最大限活用するためです。
打合せを例とすると、「打合せ」自体が本番で、「打合せのための準備」が準備です。さらに打合せは自分が主導で行うものとします。
本番を最大限活用するには、打合せの段取りも、各段階で話すことも決めておき、本番はほとんど自動運転モードで決めたことをやるだけにします。
決めたことをやるだけなので、「話すべきこと、決めるべきことが全てわかっている」状態で、迷いなく動けます。
当たり前ですが、打合せの後もプロジェクトは続くわけで、1回の打合せはプロジェクトの中のほんの一部ですが、1回1回の打合せを「本番」と捉えます。
本番を最大限活用するとは?
改めて「本番での仕事」とは何でしょう。それは打合せの議題そのものです。
- お客様の事と、その依頼をより深く理解すること
- こちらの理解をお客様と共有すること
- これからのプロジェクトについての情報を共有すること
これらが当日の議題であることが多いと思います。ここに集中できると、結構面白いです。
でも、それは「最低限」です。上記ができればミッションクリアなのですが、それは最低限であり、さらに続きがあることがあります。
「想定外の出来事」です
前職では想定外の出来事というのはわりとネガティブなことでした。
若干極端ですが、例えば「事前に採寸をせずに台車を持って行ってしまい、現場の搬入経路を使えないで大騒ぎしている時に、他の店で大変な問題が起こったと報告が入り、更に慌てる((´;ω;`))」というものです。
今はそうでは無いかもしれません。弊社に依頼を考えている、または何かしら経営やホームページにモヤモヤしたものを感じている方が目の前にいらっしゃって、机で話している状況です。
そういう場所で起こることだと、こちらが相手に集中してお話ししている間に、元々の依頼以外の事をポロっとお話しし、別のお仕事につながる、などではないでしょうか。
今の方が、より広がりがありそうです。
そんな事態になったとき、きちんと気づき、次の仕事につなげるなど、対応することができます。
たいていは、そんなラッキーは無いかもしれませんが、それはそれで「無事にミッションクリア」という事で、次の段階へ行くための準備を進めていくことになります。
そしていずれにしても、当日は、「準備で決めたことだけを行えばいい」というのはとても楽です。
そのように自分を楽にするため、楽にしておくことで本番はお客様の反応やその場の流れに集中でき、色々なことによく気が付くようになる、というのが目的で準備を進めます。これが120%で迎えられている状態です。
何を準備する?
では何を準備するのか。ここでは現在進行中のプロジェクトでのお客様との打合せを例に考えます。
その場合、明確な打合せの目的をお客様と言語化して共有する。場合によっては明確な絵で共有するための、以下を準備します
本番で話すこと
「セリフ」です。「えーと」とか「あー」とかがなるべく入らないように、本当にセリフを考えます。
本番でやる事
上の「セリフ」を話している間に、何を共有画面で見せるかを考えておきます。既存の資料では伝わり切らないと思ったら新しく資料を作ります。
それも自分のPC内で探す必要が無いように、すぐに出てくように新規で専用フォルダやリンク集を作っておくなど
自分が話すこと、確認するべきことは全て書き出しておいて、抜けもれの無いようにします。
当日自分が主導で打合せを進める場合は、打合せスタートから終わるまでの段取りを脳内シュミレーションします。
- リアルに対面なら、打合せ場所までのアクセス、時間をイメージ。
- オンラインであれば、誰がZoomやTeams等のツールを立ち上げるのか、自分が立ち上げる場合は、そのツールに不慣れであれば挙動確認をしてスムーズに使えるよう色々いじります。
- とりあえず資料は全部出しておいて、探すことがないようにしておく。当日画面に出して置きたいファイルが膨大なときは、別途ドキュメントにまとめるなどすることもあります。
そして当日の出席メンバーを思い浮かべながら、挨拶からシュミレーションします。
当日の議題・必ず確認したいことを先に言おう、あと終了時間も先に話した方がいいな…など。色々出てくるので、話す順番をノートに書いて頭を整理させたりもします。
どこまで準備する?
それらをできるだけ細かくシュミレーションします。すると抜けもれが見つかったりします。
細かくシュミレーションして、「打合せを主導して、その打合せの目的を達成する」ができそうだ、と思えるところまでです。
初めての仕事などでは、準備を始める前に、当日の段取りと準備内容を一度上司にプレゼンします。自分だけで仕上げるよりずっと精度が高く、何より大きな間違い(通路幅を採寸してなくて、サイズ違いの台車を持っていくレベルの間違い)は修正してもらえるはずです。
シュミレーションをどれだけ細かくできるか、で準備内容と本番の質は決まる
結局経験という話にはなりますが、人はそれぞれに自分の思う「準備」をしているのだと思います。経験がなければやはりシュミレーションの精度も甘くなるので、本人はシュミレーションに基づいて準備をしたつもりでも、より経験のある人やその仕事のベテランから見れば「抜け漏れ、準備不足」と思われるものではあると思います。
それでも1回1回の「準備」の質を、その時の自分でマックスに仕上げることが大事です。
準備の段階で上司にプレゼンしてみて、足りないところやズレを聞いてみるというのも準備です。まだ本番前なので。ただし、最初から何をやればいいか聞くのではなく、何をやるのか自分で考えて「プレゼン」をします。上司をお客さんだと思ってやるので、本番前に本番ができます。
人に聞いてもいいから、必ず「自分事」で能動的に準備と本番を行う事が大事です。
そして、その時の自分で行った「準備」に対して、「本番」があり、その後差を常に次回のカテにすることで、自分の規格を大きく深くしていき、だんだん「本番」で起こる出来事をカバーする「準備」をできるようになっていく、という感じだと思います。このプロセスが「自分事」でないと起こらないと思われます。
さらに、1回1回の「準備」の質をマックスで仕上げておくと、「本番との誤差」も後から活用しやすくなります。本気で準備した分、「本番との誤差」もよりリアルに感じられます。(本気度が低かった準備では、本番との誤差もあやふやになります。)
そして準備で何度も脳内シュミレーションをしていると、あらゆる仕事に対してそれが癖になり、段取り力がついてくると思います。これは便利です。全く別の仕事をしても使えます。
そうすると、「想定内」の範囲がとても広くなっていくのが自分でもわかります。そしてやたらと心配性っぽくなりますが、心配事に対する手立ても考えているので、やたらと不安がることはありません。
そんなわけで、私は準備をとても大切にしています。という話でした。
準備を大切にするハマ企画への相談はこちら